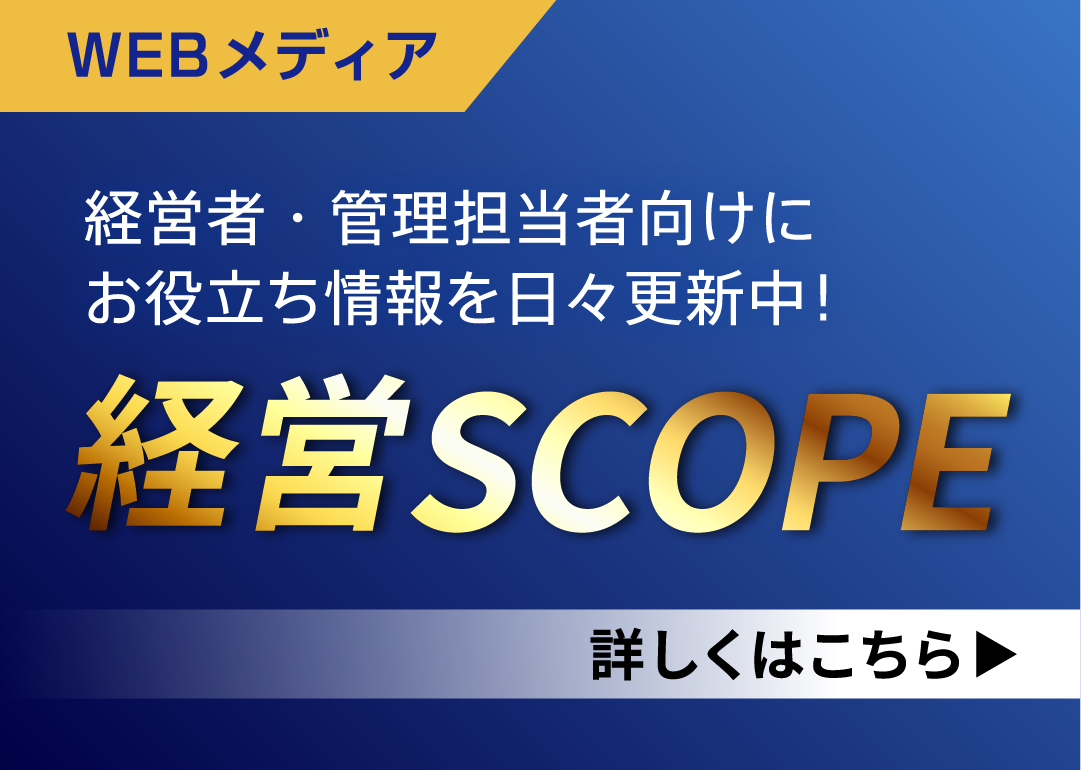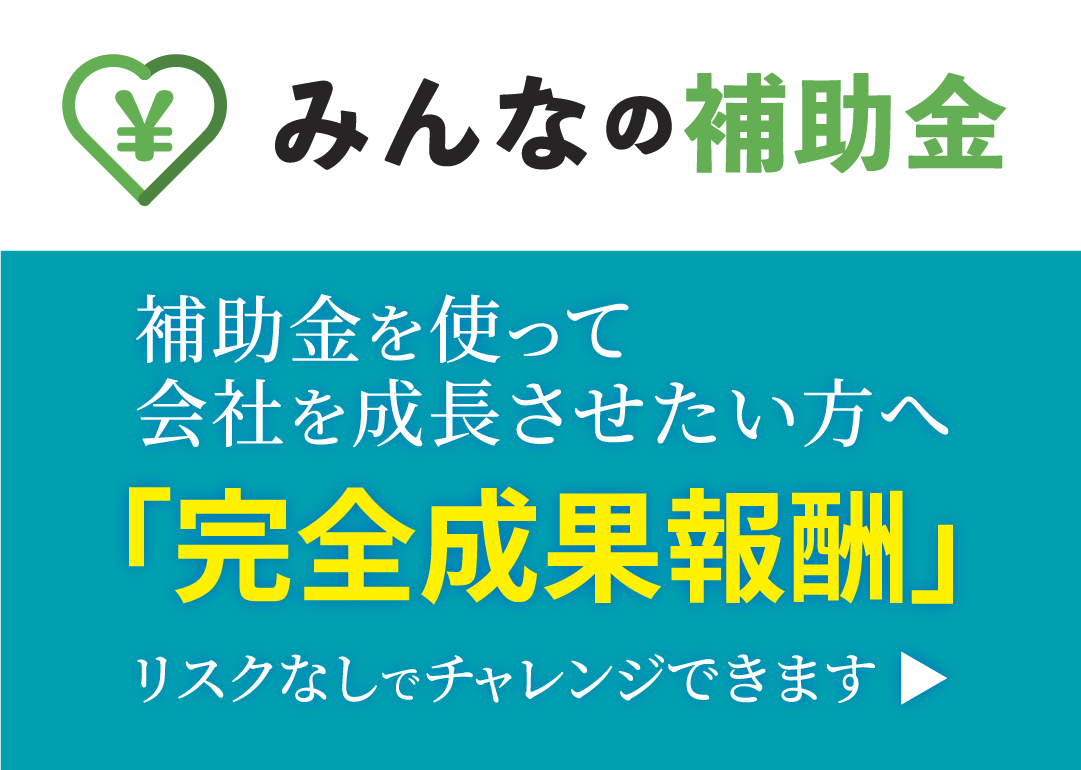経理お役立ちブログ

2025/4/19
新リース会計基準とは?改正の概要をわかりやすく解説!
日本の会計基準を定める会計基準委員会は2024年9月、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表しました。リースの会計処理についての新たな基準であり、対象となる企業は対応が必要です。本記事では、新リース基準会計の概要や対象となる企業・取引についてわかりやすく解説します。
新リース会計基準とは
新リース会計基準とは、リース取引の会計処理における新たな基準です。従来の日本会計基準におけるリース会計は、IFRS(国際会計基準)と相違点がありました。IFRSとの整合性を高めるために、「IFRS16」を基礎として日本の会計基準も変わります。
国際化に伴い、国内外の投資家が企業の経営実態を正しく理解できるようにすることも、新たな基準が設けられた背景の1つです。
新リース会計基準では、会計処理だけでなくリース取引自体の概念も変わります。従来の基準とどのような違いがあるのか、以下で詳しくみていきましょう。
新リース会計基準の対象者は?
まずは新リース会計基準の対象者を確認しましょう。すべての企業が新たな基準を適用しなければならないわけではありません。新リース会計基準を適用しなければならない事業者は、次のとおりです。
・上場企業とその子会社・関連会社
・会計監査人を設置する企業
上場企業が一般に投資を募ることは、金融商品取引法での第一種金融商品取引業に該当にします。そのため、金融商品取引法に沿った会計処理を行わなければなりません。金融商品取引法では、投資家が適正な投資判断ができるよう情報提供するために、財務諸表の作成が義務付けられています。その作成においては、新リース会計基準に沿った処理が必要です。
会計監査人を設置する会社も、客観的かつ公正な監査ができるよう情報提供するために、会計基準に基づいた処理が必要です。その際は、新たな基準に沿った処理をしなければなりません。
なお、中小企業は新リース会計基準の対象外です。ただし、中小企業であっても任意で新たな基準を適用することは可能です。
貸し手であるリース事業者の会計処理も、従来の方法でよいとされています。
新リース会計基準と従来のリース会計の違いは?
従来のリース取引は、ファイナンスリース(売買取引)・オペレーティングリース(賃貸借取引)の2種類に区分されています。しかし、新リース会計基準では、上記の区分がなくなります(単一の会計処理モデルの採用)。新リース会計基準において、リース取引と判断される場合は、ものを使用する権利である「使用権資産」を貸借対照表に計上(オンバランス)しなければなりません。つまり、従来のファイナンスリースと同様の処理を、すべてのリース取引において行うこととなります。
従来のファイナンスリースでは「リース資産」の勘定科目で資産を計上していました。新リース会計基準では、「使用権資産」という勘定科目で資産を計上します。使用権資産の取得にかかる負債は、従来の仕訳と同様に「リース負債」の勘定科目を使います。また、使用権資産はほかの固定資産と同様に、減価償却を行わなければなりません。
これまでオペレーティングリースとして取り扱っていた取引では、費用ではなく資産を計上しなければならなくなります。その結果、これまでにはなかった資産の増減が発生し、貸借対照表への影響も生じることが大きな違いです。
新リース会計基準の対象となる取引は?
一般的なリース取引として、自動車、設備などをリース会社から借りることを思い浮かべる方が多いでしょう。これらに加えて、新リース会計基準で新たにリースとしてみなされる可能性のある取引には、次のものがあります。
・不動産の賃貸借契約
・物流・輸送の委託契約
・倉庫における保管の委託契約
・電力供給の契約
・情報通信における契約
・製造の委託契約
リースかどうかを識別する際の条件には、次のものがあります。
・資産が特定されているか
・その資産の利用によって享受する経済的利益のほとんどすべてを享受する権利があるか
・資産の仕様を指図する権利があるか
契約書に「リース」の記載がなくても、上記を満たすものであればリースと判断される可能性があります。そのため、既存の契約についてあらかじめ確認しておかなければなりません。
新リース会計基準の対象外となる取引は?
リース取引であっても、次のものは新リース会計基準の対象外です。
・短期リース(リース期間が12か月以内のもの)
・少額リース(事業内容に照らして重要性が低く、金額が低いもの・新品時の原資産の価値が少額のもの)
上記の取引では、従来通り費用としての計上が認められます。
新リース会計基準の適用はいつから?
新リース会計基準の強制適用は、2027年4月1日以降開始の事業年度からです。例えば、6月決算の対象会社は、2027年7月1日から始まる事業年度から新たな基準に沿った処理を行う必要があります。
なお、2025年4月1日以降開始の事業年度から早期に適用することも可能です。
新リース会計基準への具体的な対応方法
新リース会計基準に対応するためには、新たな基準の「リース取引」に該当する取引があるかどうかの確認が必要です。該当する場合は、新たな基準に沿った処理もしなければなりません。
まずは、新リース会計基準が適用された場合に、既存のリース取引をどのように取り扱うかを確認しましょう。これまでオペレーティングリースとして費用計上していた取引も、資産計上しなければならなくなる場合があります。
既存の契約内容について、前述のリースかどうかを識別する際の条件に照らし合わせて確認しましょう。
新リース会計基準の仕訳例
これまでファイナンスリースとして資産計上していた取引では、使用する勘定科目が「リース資産」から「使用権資産」になります。オペレーティングリースとして費用計上していた取引では、勘定科目の変更だけでなく、仕訳の仕方も変わります。なお、ここでは解説しませんが、経過措置もありますので注意しておきましょう。
新リース会計基準に沿った、基本的な仕訳方法をみていきましょう。
【取引を開始したとき】
リース取引を開始したタイミングでは、支払う予定のリース料の総額と見積り利息相当額を使用権資産・リース負債の勘定科目で計上します。リース料総額と利息相当額を合わせた金額を100万円とすると、仕訳は次のようになります。
使用権資産 1,000,000 / リース負債 1,000,000
【リース料を支払ったとき】
リース料を支払ったときは、支払い方法に応じてリース負債を減らし、支払利息を計上する仕訳を行います。なお、支払利息はリース負債の残高に割引率をかけて計算します。現金でリース料10万円を支払い、そのうち支払利息が5,000円含まれる場合は、次のように仕訳をします。
リース負債 95,000/ 現金 100,000
支払利息 5,000
【使用権資産の減価償却をするとき】
新リース会計基準では、すべてのリース取引において減価償却をしなければなりません。使用権資産の減価償却費が12万円の場合の仕訳は、次のようになります。
減価償却費 120,000 / 使用権資産 120,000
まとめ
新リース会計基準では、従来のファイナンシャルリースとオペレーティングリースの区分をなくし、リース取引については原則すべて資産として計上することが必要です。上場企業や会計監査人を設置する企業は、2027年4月以降に新たな基準に沿った会計処理を行わなければなりません。遅れることなく新たな基準に対応するために、業務プロセスの見直しや新たなシステムの導入などを検討し、準備を進めていきましょう。