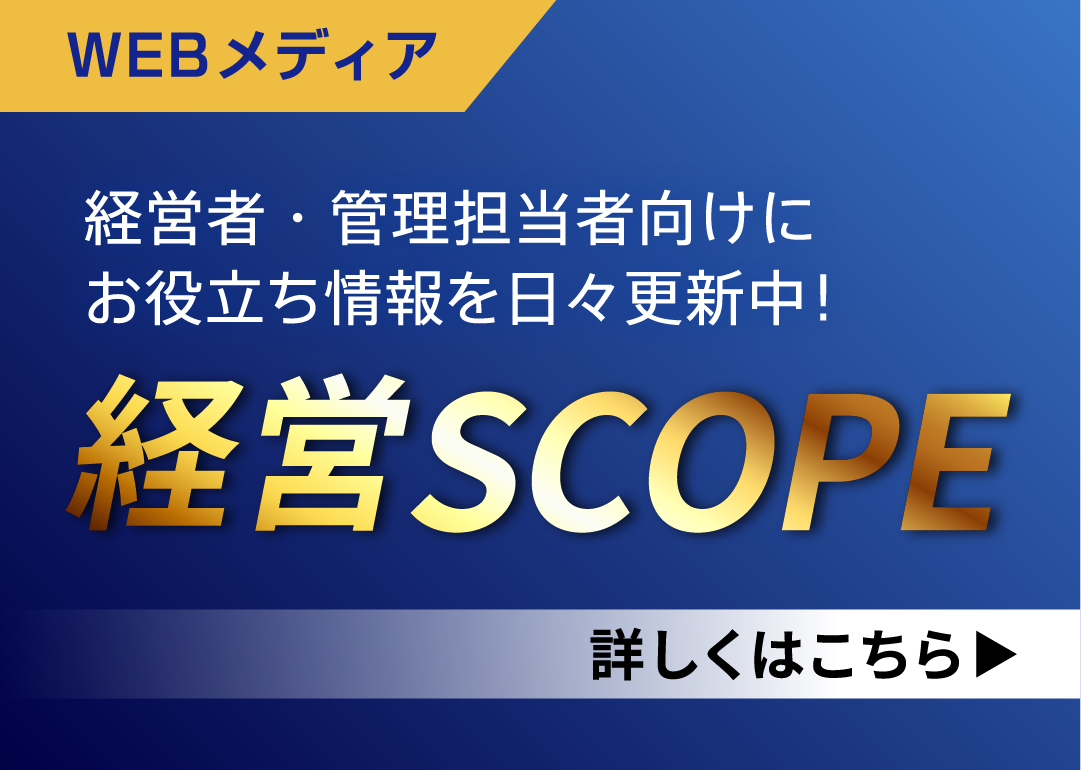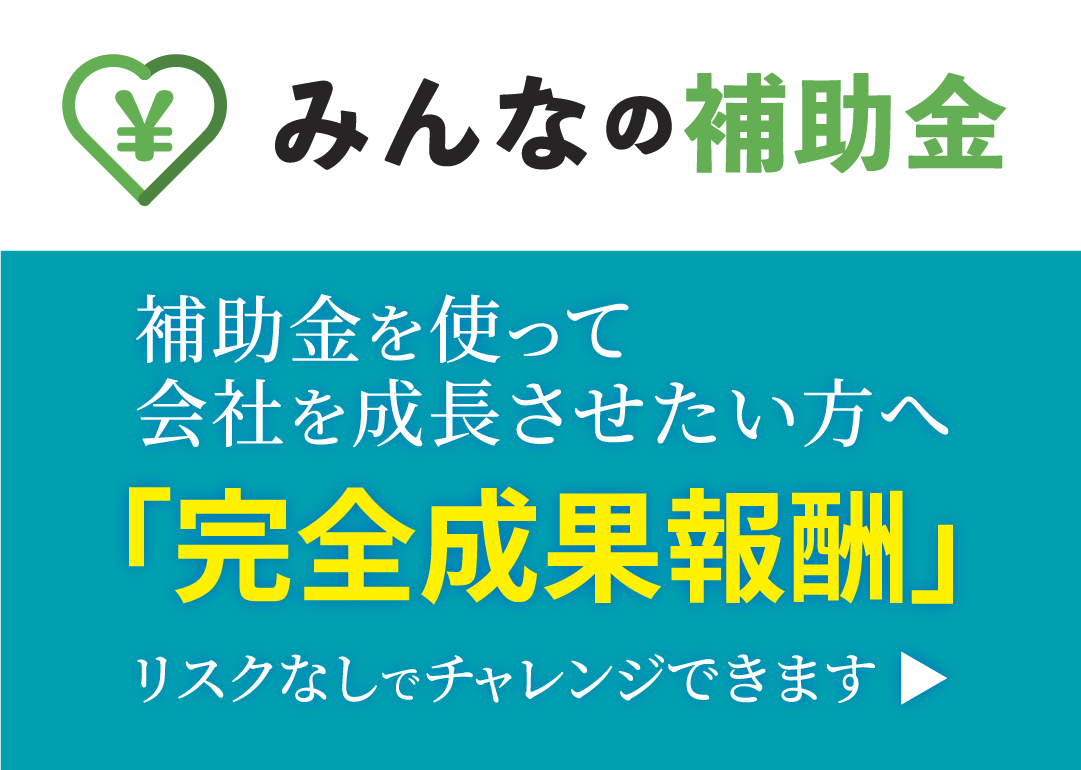経理お役立ちブログ
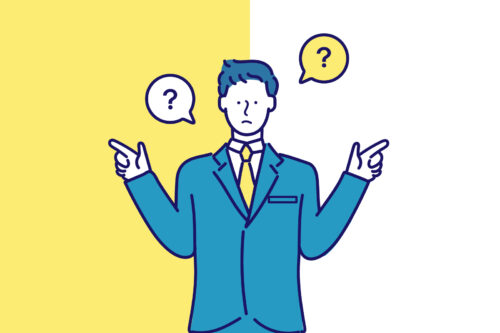
2025/4/23
経理アウトソーシング、実際どこまで任せられるの?
人手不足、専門性、コストなど企業が経理業務に抱える悩みへの対応策として経理アウトソーシングへの関心が高まっています。経理アウトソーシングで任せられる業務は多岐に渡り、記帳代行から決算業務サポート、給与計算まで可能です。また、比較的難易度の低い定型的な業務も専門性の高い業務もアウトソーシング先次第で、アウトソースすることは可能です。しかし、どこまで任せるかは企業の状況によって異なり、「どうしたらいいかわからない」という声も多く耳にします。本記事では、任せられる範囲と判断基準を徹底解説します。
経理アウトソーシングで任せられる業務一覧
経理アウトソーシングで任せられる業務は多岐に渡り、記帳代行から決算業務サポート、給与計算など様々な業務についてアウトソースすることが可能です。
- 記帳代行
- 請求書発行・債権管理
- 支払管理
- 経費精算処理
- 月次・年次決算業務サポート
- 税理士との連携業務(資料準備など)
- 会計監査対応
- 有価証券報告書・決算短信などの開示書類の作成
- 給与計算、勤怠計算
また、給与計算の中の勤怠のチェックなどのように、上記の項目の単位ではなく、さらに細分化した業務の単位でアウトソースすることも可能です。
これから、どこまでアウトソーシングをするのか検討する場合には、表や図で「任せやすい業務/一部注意が必要/自社対応が望ましい業務」を分けて視覚的に整理すると効果的でしょう。
(関連記事)必要に応じて使える経理業務のアウトソーシング(経理代行)
どこまで経理アウトソーシングするかどうか?判断ポイント5つ
経理業務の効率化、経理部の負担減少などを目的として、経理アウトソーシングを検討する際、どのような業務についてアウトソーシングをするのがよいのでしょうか。5つの判断ポイントを解説します。
業務の定型性(ルーティンワークかどうか)
定型業務は、マニュアル化や手順化がしやすく、アウトソーシングしやすい業務です。非定型業務は、状況判断や臨機応変な対応が求められる業務で、基本的には社内対応が望ましい業務である一方、アウトソーシングが成功すれば、大幅に業務負荷を減らすことが可能となります。
情報の秘匿性(社外に出しても問題ないか)
顧客情報や経営戦略など、外部に漏れるとリスクがある情報を扱う業務は、原則として社内対応が望まれます。公開情報や機密性の低い情報を扱う業務であればアウトソーシングが可能です。
経理アウトソーシングする場合、公開情報や機密性の低い情報のみを扱う部分をアウトソースすることは難しいでしょう。アウトソーシング会社が一定のセキュリティ対策を講じている場合には、機密情報を取り扱う業務をアウトソースすることも可能です。アウトソーシング会社がどのようなセキュリティ対策を講じているかを確認しましょう。
業務の難易度・専門性
高度なスキルや業界特有の知識が必要な業務については、専門のアウトソーシング会社へアウトソースすることも選択肢となります。一般的なスキルで対応可能な業務については、自社での要員育成のハードルも比較的低く、社内対応しやすい業務です。ただし、外注コストが安ければアウトソーシングすることも考えられますので、コスト比較がポイントとなります。
社内との連携度(社内情報を多く必要とするか)
部門間の連携や社内情報へのアクセスが頻繁に必要な場合は、社内での対応がスムーズとなります。一方、社内との連携をそれほど必要とせず、独立して処理できる業務はアウトソーシングに向いています。
なお、社内チャットを導入しているなど、社内でのコミュニケーションを取りやすい状況を作っていれば、アウトソーシング会社と社内の人が直接やりとりをして必要な情報を伝えることも可能です。
緊急対応の要否
突発的な対応や迅速な判断が必要な業務は、社内対応が望ましい業務となります。一方、納期に余裕があり、計画的に進められる業務はアウトソーシングしやすい業務となります。
これらの評価ポイントを踏まえて、整理・検討したとしても、実際のところ「どこまで任せるのが適正なのか」は初めてみるまで判断がつかないこともあります。スモールスタートからはじめ、柔軟に見直していく方法も一つの選択肢となります。
任せすぎの落とし穴とその対策
経理アウトソーシングはうまくいくと経理業務の効率化、経理部の負担減少に繋がりますが、任せすぎにも落とし穴があります。落とし穴と対策を知っておきましょう。
任せすぎの落とし穴
自社にノウハウが残らなくなる
アウトソーシングを進めると、業務に必要なノウハウが自社に残らなくなる可能性があります。状況が変わり、業務を社内に戻そうとしても、ノウハウがなく社内で処理することができなくなります。
外部に依存しすぎるリスク
外部に依存しすぎて社内にわかる人間がいないという状態になってしまうと、ミスが起こっていても社内の誰も気づかない、ということが起こる可能性があります。
情報のやりとりのタイムラグ
レスポンスの早いアウトソーシング会社を選定したとしても、社内とまったく同じように情報のやりとりをすることは難しいでしょう。緊急性の高い業務が生じたが、連絡がつかず、結局自社対応することになる、という状況も考えられます。
対策
これらの落とし穴への対策としては、業務マニュアルの整備、定期的なレビュー、業務分担の見直しなどが考えられます。経理アウトソーシングの導入後、うまく回るまで定着するには数か月~一年程度の時間がかかります。経理アウトソーシングを成功させるためには、問題が起こったら都度、共有し、文書化を進めていくことが最も重要です。
会社規模別:実際にどこまで任せる?
会社規模別に実際どこまで経理アウトソーシングできるのか、事例をご紹介します。
小規模企業
小規模企業の場合は、記帳~給与計算~請求・支払といった経理業務のほぼすべてをアウトソーシングして、経理要員を配置しないことが考えられます。この場合、経理要員の人件費は節約できます。
中規模~大企業
中規模~大企業の場合は、すべての経理業務をアウトソーシングすることは難しいでしょう。パートや派遣社員などの入れ替わりが多い会社であれば、経費精算や請求書発行など定型業務のみアウトソーシングすれば、パートや派遣社員が変わる都度の退職・育成という手間が省けます。専門性の高い業務を任せる人材がいないということであれば、決算業務、税理士・監査法人対応、開示・IR業務などの専門性が高いアウトソーシングを依頼することが考えられます。
ベンチャー企業
ベンチャー企業の場合、スタートアップ期はフルアウトソースし、会社規模が大きくなれば経理要員を採用し、徐々に内製化していくことが考えられます。
(関連記事)スタートアップこそ経理アウトソーシングを活用すべき理由とは?
まとめ:信頼できるパートナーを選び、無理のない範囲で
経理アウトソーシングで任せられる業務は多岐に渡るため、「全部任せる」のではなく、「何を、なぜ任せるか」を整理することが大事でしょう。整理・検討したとしても、実際のところ「どこまで任せるのが適正なのか」は初めてみるまで判断がつかないこともあります。スモールスタートからはじめ、柔軟に見直していく方法も一つの選択肢となります。
これから経理アウトソーシングを導入する際は、アウトソーシング先(パートナー)選びも重要です。こちらの記事もぜひ参考にしてください。
(関連記事)経理アウトソーシングで失敗しないための委託先の選び方